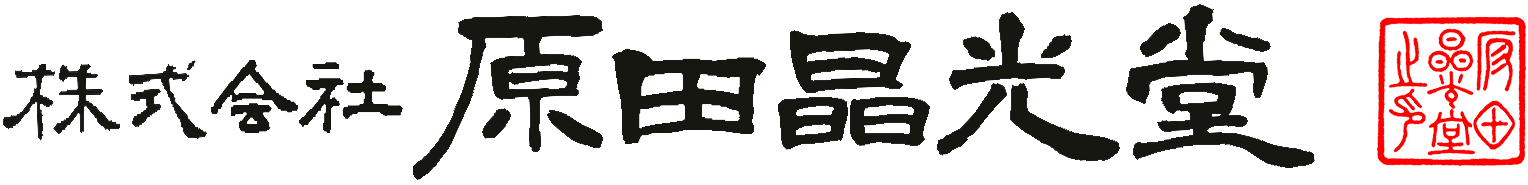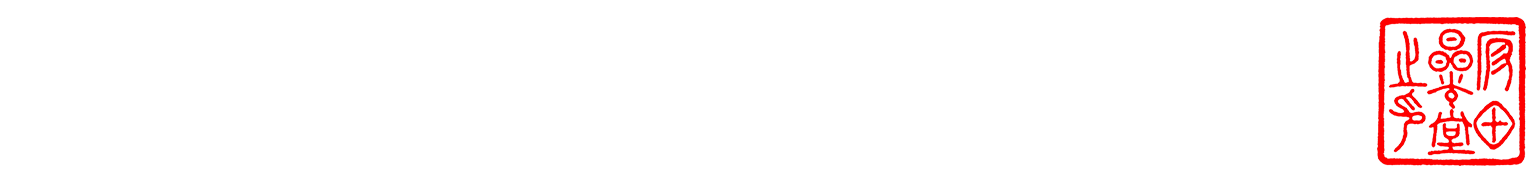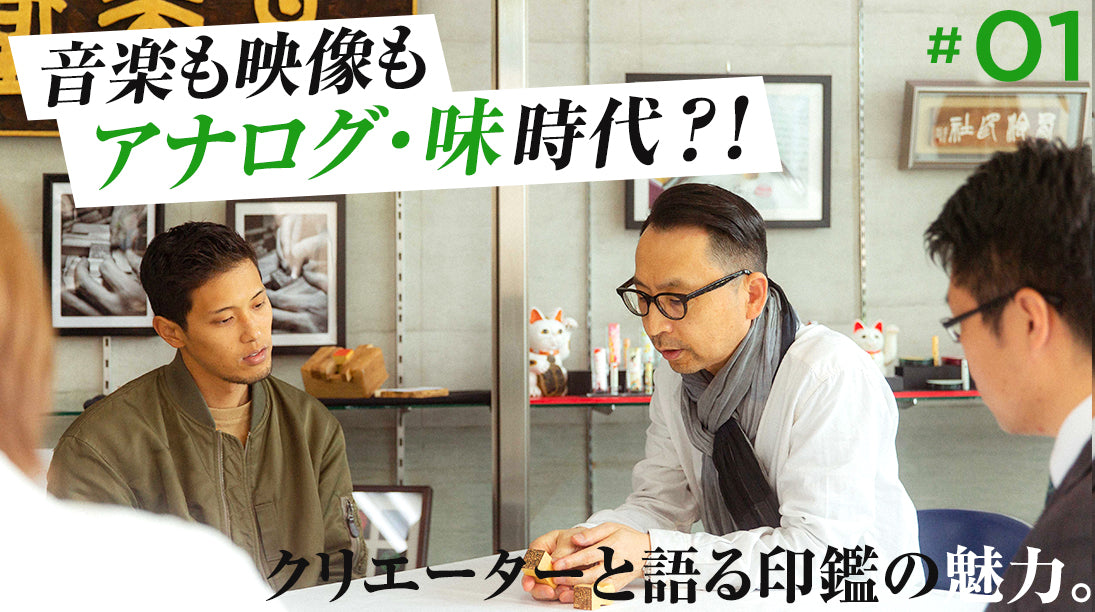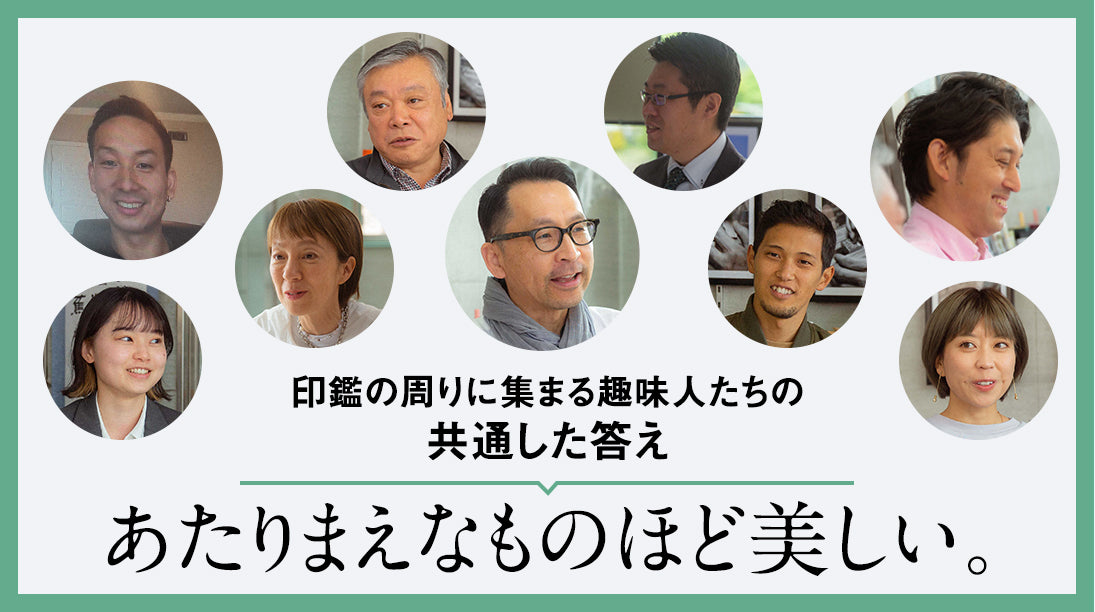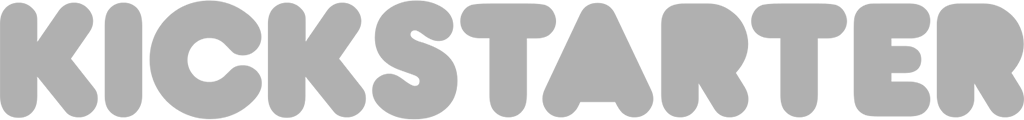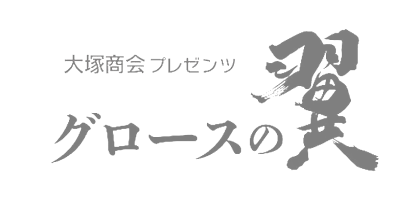06:中途半端はできないんだよ。だって歴史の一部だからさ。
家安:genjimetal が話題になって取材も増えた。確かに印鑑の歴史の中ではなかなか進化を遂げた逸品だと思うんですが、改めて genjimetal の価値ってなんだと思いますか?
原田:もちろん構造の素晴らしさは特筆すべきことなんだけど、何よりも職人さんが文字を手書きでデザインしているということだとと思うんですよ。

家安:意外と印鑑の原点!?
原田:そう。文字が消えたり出たりする構造を可能にしようとすると、文字と余白いずれも繋がっている必要がある。でもご存じの通り、印って文字なんですよ。それも歴史と技術、意味に裏付けされた確かなもの。それを制約の中でいかに伝わってきた伝統を踏襲しながら新しい文字を作り出し、それが未来においても新しい伝統となれるかは職人にしかできないこと。ね、小林さん、二宮さん。


家安:印章職人さんとして、金属から文字が出るとかお聞きになって抵抗とかなかったですか?
小林:原田社長から事前にお話を聞いていて、むしろ面白いなと思っていましたよ。だって金属を加工しておられるのも職人さんでしょう?最新技術の職人技と私たちの古い技が出会うこと、面白いですよね。とはいえ、やり始めたら思った以上に大変でしたが!
家安:どんなところが大変だったんですか?
小林:篆書体(てんしょたい)ってはるか昔から存在し使われてきた文字で、それを自分なりに安易に変形できないんですよ。例えばひらがなの”く”を反転させたら意味がわからなくなるでしょう?そのぐらい大変なこと。だって全てに意味がありますからね。容易には崩せませんよね。


小林:でも genjimetal においてはこのシステムを形にするために文字だけでなく余白も全て繋がっている必要があった。すなわち文字に切れ目が適切に入らなければいけない。そうしないと余白部分が島のように取り残される部分が出てしまうから。だからどこを変えるか、判断は自分にかかっていますよね。
原田:今、見ていただいているものって拡大プリントですが実際は18mmという小さな円形の中。その細やかさがわかりますよね。



二宮:小林さんがされたものを全て拝見して、自分も作り始めました。例えばこの枠文字は genjimetalのメカっぽさを尊重して篆書体(てんしょたい)や印相体(いんそうたい)を元に直線的な線使いを行い、枠の淵さえも文字の一部として利用することを行っています。またこの刀文字(かたなもじ)はメタルの持つ硬質な質感がまるで刀みたいだと思い、ハンコではあえて馴染みのない文字ではあるのですが、ハンコの側面に彫る側款と言 ってガリっと削りを入れる刀の感じを残した文字を参考にしてデザインしてみました。
小林:文字作りって今までのセオリーをある意味崩さなきゃいけないからね。
原田:なかなか大変なお願いをしまして、申し訳ない!
小林:例えばここは繋げたくないけど繋ぐ、とか。繋いで文字の意味を見せなきゃとか、隙間もある程度必要だけどあまり規則的でも美しくないし、とか。


二宮:篆書古印体(てんしょこいんたい)も手掛けたのですが、原田社長からもっと正統派なものも作ってほしいと言われ。元々ハンコっぽくないものをオーダーされていたんですが、苦笑。
この篆書古印体(こいんたい)って墨だまりみたいなものが味になる書体で、例えば腐食して字が途切れたり、経年劣化で文字が切れていたり、そんなイメージを使って文字の切れ目を考えたりしました。
小林:実際に筆で書くならどうなるんだろうということを気にして書き順を考えて切れ目を考えたりしています。結構神経を使うんですよ。

原田:文字デザインって誰が携わるかが大切で、基本genjimetalって高いものだし一生ものだからきちんとしたものを作り、お渡ししたいんですよね。
小林:この genjimetal の文字を作るにあたり、社長にお願いしたことがあるんですが、この文字たちはいわゆる正確な文字ではないんですよ。消えたり出たりする構造を可能にするためにつながりや切れ目を調整した文字なのでアレンジなんですよね。この世界のための文字なんです。

原田:小林さんのこの話が重みがあるのは、こういう姿勢なんですよ。適当に切り込み入れて仕上げることもできるんです。文字の歴史を知らなくてもできるかもしれない。でもそれは違うんですよ。
小林:文字の歴史は人の歴史と同じで、いろんな形を経て形を変えて今に至るんです。そして今は未来に続くもの。進化の途中なんです。切ってしまう、ただその場だけいいものを作ることは未来につながる進化にはならないんですよ。
原田:印鑑の歴史を引き継ぐものとしての役割なんです。
小林:進化の一部だから博物館に過去のものたちと並ぶ次のものを作っているんです。歴史を作っていると言えるのではないかと。近年ね、印鑑の衰退の原因はデジタル化と言われていますが、それより前に事務用品になってしまったことが問題なんです。元々ハンコは自分の身代わり、自分を表現するものであったから、ハンコを見るとその人の人となりわかったんですよ。ハンコを押す時って契約だったり人生の大切な瞬間でしょう?それをどのように捉えているか、歪んだハンコや欠けたものはね、そういう姿勢が見えてしまう。
昔はハンコ屋とは言わなくて御印師と呼ばれていたんですよ。ハンコは偉い人しか持てなかったので、その人の命を受けて作るわけです。だから刀や紙を御刀師、御表具師といったようにね。

山下:全てが繋がっていますね、キーワードだなと思いました。日本文化って神社の鏡もそうですが、ありのままを映し出す文化でもあると思うんですよね。
小林:必ず印面を見てから押すでしょう?そうしないと上下とか向きが確認できないですよね。それは実際的な意味もありますが、印が自分の身代わりだから自分を映し出すかのように押すんです。今回の印鑑、印面が鏡面であることでまさにその意味を体現しましたね。
二宮:自分が映り込むのが面白いですね。もっと写そうと思うと凹ませたりして広角レンズみたいに作り込むとかも面白いですね。
原田:これまた次の挑戦が始まりそうだ!

二宮:海外でも漢字は人気ですよ。特に意味を伝えるとみんな関心を示します。小さなイベントで習字で名前を書いて渡すこともあるんですが、みんな興味津々です。ハンコの価値を伝えることも大切ですが、そもそものところで漢字や文字の意味を伝えることも大切ですね。